一隅を照らそう
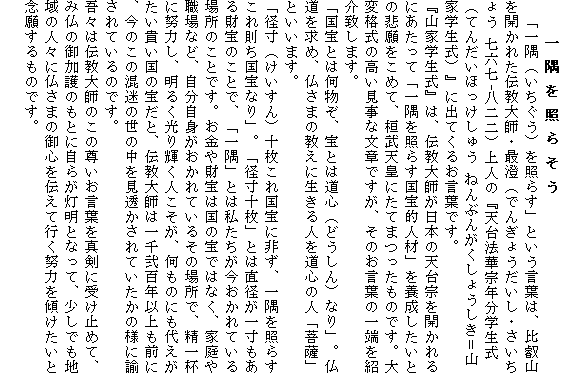
 |
第五十七世 観音教寺 住職 濱名 徳永 大僧正 |
花見に就いて思う
【特別展「櫻-粋な花見」(平成20年3月1日~4月30日)によせて】
同じ東洋の国でも、中国で花と言えば牡丹を指すそうだが、吾が国で花と言えば、桜を思い浮かべるに違いない。何故日本人はそれ程までに桜を愛で、心を打たれるのであろう。桜の美しさは、その散り際にあると言われるが、あの可憐な小さな花弁が、そよ風に誘われてはらはらと吹き散るすがたは、正にこの世のものとは思えぬ美事さがあり、あわれさがある。そのあわれさこそが日本人の心を把えて離さないのではなかろうか。
芭蕉十大弟子の一人に数えられる採茶庵杉風は、「散しあと咲かぬさきこそ花恋し」と言う一句を残している。如何にも余韻のある名句である。又同じ杉風を始祖とする飛鳥園七世西翁一叟にも「奪われし心もどりぬ夜の花」なる一句がある。この一句を見れば十分うかがえる様に、私の如き老人から見ると、一昔前の人達の花見と、現代の若い人達の花見とでは、同じ花見でも、そのあり様は、大分変わって来ているのではないであろうかと思うのである。
例えば今日花見の時期が終ると、何処の桜の名所でも、トラック何百台ものゴミの山が出来、その始末に困ると言われる。
一昔前、茶人達は樺細工と称した桜の皮を使用した茶入れなど小物を事のほか愛でて使用して来た。何の変哲もない桜の皮なのだが、そこに何とも言えない味がある。この桜の皮のあり様の中に茶人達は一体何を見ていたのであろう。
考えすぎだと笑われるかも知れないが、私は、桜の木が見事な花を咲かせる為に、あの皮は一生懸命樹木を守って来たのであって、この皮の力がなければ、あの美しい桜の花を吾々は眼にする事すら出来ないのだと考えていたからこそ、カバ細工が珍重されて来たのではなかろうか、換言すれば、日本人のもののあわれさの根元は、この辺に秘められていると思えてならない。
人間は萬物の霊長と自らを誇るけれども、吾々は地球の風土の影響を強烈に受け続けているのであって、人類の思考の相異は、この母なる地球の多様性に起因すると言っても過言ではあるまい。
人類の相互理解は、永年人々を育み育てて来たお互いの先祖が受継いで来た風土を正しく理解し、その認識の下に相互理解を深めて行く処から始めて行かなければならないのであろう。
その観点に立てば、これ程日本人の心を把えて離さない桜に就いて、もっともっと多くの情報を吾々日本人は外国の人々に発信する必要があるのではなかろうか。又吾々は、日本人の先祖が桜の花に何を感じ、それを如何に咀嚼し、日本の伝統文化の中に如何に生かし続け、吾々の血となし肉となして来たのかを、ここらで改めて振り返って見る事が求められているのではあるまいか、この特別展はささやかなものではあるが、その第一歩としたいと念願する。

桜の花が刻まれた鍔(ツバ)
「風月相知」の雅印に思う 【平成19年6月】
たまたま某店の古書資料目録に眼を通していましたら、書家町春草愛蔵の二代中村蘭台刻の印三顆が紹介されていました。印材及び篆刻に就いては私は全くの素人ですが、文人達にめでられた鶏血石と言う印材の見事な色合には驚嘆いたしました。自分の作品にこんな美しい石材に、しかも高名な篆刻家の手になった雅印を捺す事が出来た書家は、どの様な心境であったのであろうかと想像すると、何とも羨ましい、気持ちになりました。
雅印と言えば、今から五十年以上も前の事ですが、先代徳潤大僧正から一顆の雅印を見せられた事があります。当時は未だ一介の学生であった私には、俗に言う猫に小判で、全く興味も関心もありませんでしたが、そう言えば確か蘭台刻ではなかったかと思い出し、老師の遺品を調べてみましたところ、二代蘭台刻である事を確認致しました。(二代蘭台は篆刻家として初めて日本芸術院賞を受賞した事で著名)そして箱書には、
長野清水屋先代所蔵
昭和二十七年五月 受之徳潤
と記されています。先代は長野の善光寺大勧進住職水尾大僧正の下で暫く副住職を拝命していた事があり、その功績に依り、自坊観行院に善光寺関東別院の名称を頂いた関係もあって、当然善光寺門前の老舗の旅館である清水屋さんとの交流が生じたものと思われます。
さて雅印は、「風月相知」と刻まれています。この場合の〝風〟は文字通りさわやかに流れ渡る初夏の風などを表すわけでしょうが、風格などと言う場合には、群を抜いたその人の人格の高さや、他人には真似できない見事な生きざまや心が、伝わって来て、自ら頭が下がると言う様な場合などにも使われます。
次に〝月〟は、太陽の光とは異なった澄明な光の故に、それ程明るくはないのに、むしろそれ故に太陽の光では見透す事の出来ない、何かを吾々に教えてくれる事があります。人間の感覚は或る意味では全く不自由で、見る人の心に依って、全く同じものを見ていながら、そこから反対の事を感じ取る事がままあります。
禅家で盛んに使われる大悟徹底すると言う言葉の奥にはこんな人間の認識の盲点が隠されているのではないでしょうか。
次に〝相知る〟ですが、人の生い立ちなどと言う大それた事は別としても、生々流転するこの地球の営みから、吾々が学び取らねばならぬ事は山程あって、何度生まれ変わって来ても、その全てを感じ取る事は不可能なのでしょうが、その片鱗でもうかがい知る事が出来た人間は、誠に幸である。と言う程の意味でしょうか。
もう一つ印影でも明瞭の様に、風と相との字の間が隔絶していない事に私は注目したいと思います。最初瑾ではないかと思ったのですが、高名な篆刻家がそんな事をする筈がないと考えました。同様に清水屋さんも、名だたる信心家であったと聞いていますので、傷のあるものをくださる訳もない。良く見るとどうも意図的にほっていると思われます。
大自然の営みは吾々人間から見れば想像を超えたものであり、それを受ける人の心によって無限の糧を与えてくれるもの、それは?然一体であって風とか月とか本来は区別出来る存在なのではないのでしょう。この小さい石の中に、無限の意味を込める篆刻の世界の広さと深さに、しばし心を打たれた次第です。
|
風月相知(縦横幅約2.7㎝) |
篆刻 刻面 |
不滅の燈明のお話【平成18年5月】
 |
伝教大師は 『あきらけく後の佛のみ世まても 光つたへよ法のともし火』 (勅撰新拾遺和歌集) と詠まれ、不滅の燈明を比叡山上に高々と掲げられました。以来千二百有余年、根本中堂に輝き続ける不滅の燈明は日本天台の象徴とされ、宗祖伝教大師のお諭しに応える吾が宗徒の誇りとして、大切に護持されてきました。 当山は伝教大師が創立された関東天台の旧制伴頭拝領寺院にその名を連ねる役寺として、宗祖のご精神を奉じて、この燈明をしっかり保持して行き度いと念願しております。 又、吾師・当山五十六世徳潤大僧正(1887~1954年)は晩年、下記の歌を残しています。宗祖の立宗の御精神に答えんとする吾師の面目躍如たるものがあると思いますので、自戒の意味を含めて御覧に入れます。 『往生は弥陀にまかせてひたすらに まもり行かばや法のともしび』 徳潤 |


